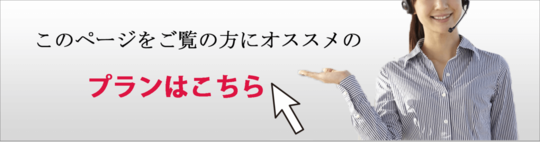- 相続放棄するときの注意点は?
相続放棄するときの注意点は?
10年以上疎遠だった父が亡くなったとの知らせがありました。生前、父は借家に住んでおり、資産は何もありませんが、遺産の整理をしていたら借金があることが分かりました。兄弟で相続放棄することを検討していますが、相続放棄するにあたり注意する点はありますでしょうか?
家庭裁判所で相続放棄することをお勧めします。
今回のケースでは、被相続人と相続人は10年以上疎遠で、被相続人の生前の生活状況を把握していないとのことでした。また、被相続人に資産は何もなく、借金があるということでしたので、当センターに相続放棄の手続のご依頼をいただき、家庭裁判所で相続放棄の手続きをし、無事に受理されました。
~相続放棄とは~
相続放棄とは、亡くなった人のプラスの財産も、借金などのマイナス財産も全てを相続しないようにし、相続放棄した人は初めから相続人ではなかったということにする手続です。相続放棄をすると、資産を相続することが出来なくなりますが、借金などのマイナスの財産の支払い義務もなくなります。
よく勘違いされる点は、遺産分割協議で資産を放棄すること=相続放棄ではないということです。遺産分割協議で資産を放棄したとしても、借金の支払義務はなくなりませんので、被相続人のマイナスの財産を相続したくないという場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続をする必要があります。
~相続放棄の手続の方法と期限~
相続の開始を知った時から3カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をします。相続放棄には3ヶ月という期限がありますので、期限内に必要書類を収集・作成し家庭裁判所に提出する必要があります。
相続放棄は、「自己のために相続があったことを知ってから3カ月以内」にしなければならない、と民法に定められています。この「自己のための相続」とは、単に被相続人の亡くなった時ではなく、自分が相続人であることを自覚し、相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常であれば認識できたであろう時とされています。
~3カ月以内に相続放棄をすることができない場合~
相続放棄をするかどうかを決めるには、相続財産の内容を調査し、本当にプラス財産よりもマイナス財産が多いのかなどを確認する必要があります。相続放棄をすると、あとでプラス財産の方が多かったと分かった場合も撤回することができなくなってしまうため、注意が必要です。
しかし、相続を知ってから3カ月以内に、相続財産の調査を行うことが難しい場合などは、家庭裁判所に申立てをすると期間の延長が認められる場合があります。
相続放棄の手続をしたいけど、どこから手をつけてよいか分からない、手続きをしている時間がない、被相続人が亡くなって3ヶ月以上経過しているけど、私の場合は相続放棄の手続きは間に合うのか、とお悩みの方は当センターまで直接ご相談ください。