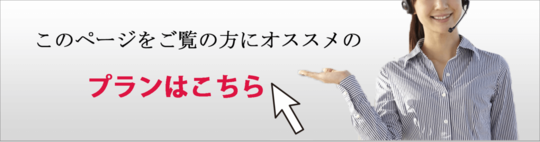自筆証書遺言を作成する場合の注意点は?
自筆証書遺言を作成する場合に注意する点を教えてください。
私には子がいますが、甥と姪にも遺産を分けたいと考えています。そこで、遺言書を自分で作成して遺しておこうと思うのですが、どのような点に気をつけて作成すればよいでしょうか?
遺言書の全文、作成日、氏名を自書で記載して押印することが必要です。
自筆証書遺言は、以下の点に気をつけて作成する必要があります。
(1) 全文を自分で書く
(2) 日付を記載する
(3) 氏名を記載する
(4) 押印する
(5) 記載内容の訂正等を決められた方法で行う
~全文を自分で書く~
自筆証書遺言は全文を必ず自分で書かなくてはいけません。
パソコンやワープロで作成したものや、他の人に代筆してもらったものは無効となります。
また、遺言書は必ず書面で遺す必要があり、録音や録画された遺言も無効です。
~日付を記載する~
日付は遺言書を作成した日付を明確にし、仮に複数の遺言書があった場合に、優先関係などを判断する上でとても重要となるため、「年月日」で記載することが必要です。
これも必ず自分で書く必要があり、記載がないと遺言書自体が無効となります。
~氏名の記載、押印~
氏名も自分で書く必要があります。ペンネームや芸名でも可能ですが、これは本人との同一性が確実でない場合は無効となる可能性があるため、戸籍通りのフルネームで書くことをお勧めします。
また、印鑑が無い遺言書は無効となるため、押印が必要です。
押印は、認印でも問題ありませんが、実印で押印することをお勧めします。
~記載内容を間違った場合の訂正~
記載内容の訂正や追加は決められた方法で行う必要があります。
訂正する場所を指示し、訂正した旨の記載を付け加え署名して、訂正箇所に押印することが必要です。形式が間違っていた場合は、無効となる可能性があります。
訂正や追加がある場合は、最初から書き直すことをお勧めします。
遺言書の内容はできるだけ具体的にわかりやすい表現で記載しましょう。
財産を特定する際には、不動産は登記簿謄本通りに記載し、預貯金の場合は銀行名、支店名、口座番号を記載するなど、詳細に記載するようにしましょう。
また、自筆証書遺言書は改ざん等のリスクを避けるため、封筒に封印し、遺族が発見できるような場所や貸金庫などの安全な場所に保管することをお勧めします。
~公正証書遺言の活用をお勧めします~
以上のように自筆証書遺言は費用をかけずに公証役場まで足を運ぶ必要がないため、手軽に作成ができてよい部分もあります。
しかし、せっかく作成した遺言が無効になるリスク、紛失や改善のリスクがあり、遺言執行者の定めなどの大事な記載事項が欠けていると、相続人が後から手続きの段階で非常に苦労することになります。
相続人に手間をかけることなく、確実に遺言書の内容を実現したいという方は、公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。