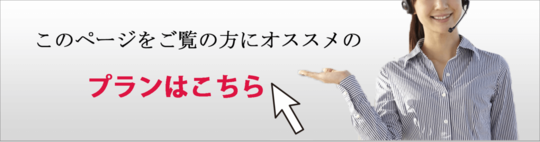遺言書がある場合の手続きはどうしたらいいですか?
遺言書がある場合の相続手続きはどうしたらいいですか?
先日父が亡くなりました。亡くなった父の遺品整理をしていたところ、父の部屋で遺言書を見つけました。この後の相続の手続きはどうしたらよいでしょうか?
遺言書の形式によって、その後の手続きが違います。
見つかった遺言書が、自筆証書遺言(亡くなった方ご自身で全文を書いた遺言書)の場合は、家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。公正証書遺言(公証役場で作成した遺言書)の場合は、検認の手続きは不要で、遺言執行者が遺言の内容に従って手続を進めていくことになります。
~自筆証書遺言の場合はまず検認手続きを~
自筆証書遺言の場合、遺言書を見つけた方や保管していた方は、できるだけ速やかに遺言書を、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出して、検認手続きをする必要があります。
検認手続では、全ての相続人に対し遺言書の存在を家庭裁判所から知らせ、相続人が家庭裁判所に集まった中で開封し、その状態や日付、署名など遺言書の内容を明確にします。
検認の趣旨は、遺言書が偽造・変造される危険を防ぐことであり、遺言書自体が有効であるかを判断する手続きではありません。
この検認手続きを経ないと、不動産の名義変更や預金や株式の解約手続きで遺言書を利用することができませんので、検認手続きは必ず行う必要があります。
検認手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て集めて、家庭裁判所に提出しなければならないため、自筆証書遺言を見つけたけど自分で手続をするのは大変だから手続の代行をお願いしたいという方は、当センターまでご相談ください。
~公正証書遺言の場合は遺言執行者が手続を進めます~
公正証書遺言の場合には、作成する際に公証人が関与しているため、この検認の手続きは不要になります。相続人が家庭裁判所に集まることなく、遺言執行者がすぐに遺言書の内容に沿って、相続の手続を進めることができるので、後々のことを考えると公正証書で遺言を作成しておいた方が手続が相続人の手間が省け、スムーズに進みます。
公正証書遺言では、通常、遺言執行者が指定されています。遺言者が亡くなった後に、遺言執行者は、遺言書に書かれている内容を、すべての相続人や受遺者に知らせる必要があります。その後、遺言執行者が遺言に書かれた内容どおりに、不動産の名義変更や、預貯金・株式等の資産の相続手続を速やかに行います。
遺言執行者には相続人のうちの誰かが指定されることが多いですが、遺言執行者が相続手続きに不慣れな場合や、時間がないので手続きを専門家に任せたいという場合は、司法書士や税理士に相続手続きを任せることもできます。
遺言執行者に指定されたけど、相続手続きは専門家に任せたいという方は当センターまでお気軽にご相談ください。